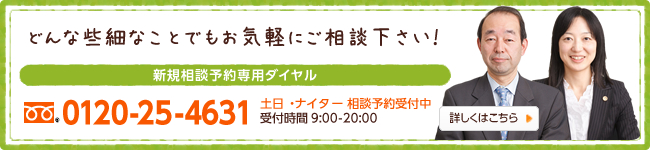標準算定方式は、父母双方の収入、子の人数、年齢により、簡易迅速に養育費の算定ができる基準となっていますが、仮に養育費を支払う側(義務者)の年収が900万円であるとしても、そこから標準算定方式を当てはめ、養育費を決められない場合もあります。
今回はそのような養育費の修正要素について解説をしていきます。
養育費の支払い側(義務者)が給与所得者で、その年収が900万円だった場合の養育費の算定につき、基準から減額修正すべき要素
養育費とは

養育費は、離婚後、子が経済的社会的に自立するまでの間、その衣食住や教育・医療等のために必要となる費用です。
法律上、親は子を扶養する義務があり、離婚をしても配偶者と子が親子であるという関係性に変わりはないため、離婚後、子を監護しない親は子を監護する親に対して養育費を支払わなければならず、離婚時には養育費の支払いについて定める必要があるとされています。
養育費をいつまでもらうことができるかについては、成人年齢が18歳に引き下げられてからも基本的には子が満20歳に達するまでとされることが多いのですが、20歳となった時点でその時点で子が大学等に進学している場合には満22歳に達するまでとされることもありますし、逆に子が高卒で働きだしたという場合には終期を早めるということもあります。
要するに、養育費の終期については「子が経済的社会的に自立するまで」であるといえます。
養育費の相場は?

従前の夫婦の生活状況により離婚後の子の衣食住や教育・医療等のために必要と考える費用は区々です。
離婚協議の中で夫婦が納得して離婚後の子の養育費の金額を定めるのであればその金額に特段の制限はありませんが、話し合いがまとまらないという場合には家庭裁判所での調停や審判により養育費の金額を決める必要が出てきます。
実務上、家庭裁判所においては、夫婦双方の収入や子の人数・年齢に応じて養育費の金額を一律に算定する算定表という資料を用いて離婚後の子の養育費を決めています。
そのため、家庭裁判所が用いる算定表により計算された養育費の金額が養育費の相場であると言えます。
算定表とは?

算定表は標準算定方式 という計算方法に基づき計算される額を、分かりやすく表にしたもので、裁判所が、簡易迅速性、予測可能性、公正性を確保する養育費の算定方法として公表しています。
現在、公表されている算定表は令和元年12月に改訂されたもので従前のものと比較する形で新算定表と呼ばれています。
算定表は以下の裁判所のホームページにPDFデータの形で掲載されていますので、インターネット環境があればいつでも確認することができます。
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html
配偶者の年収が900万円の場合の養育費の相場

義務者の年収が900万円の場合、算定表上は養育費を受け取る側(権利者)の年収、子の人数、子の年齢によって、8万円程度から22万円程度までの額が想定されるところです。
標準算定方式における養育費の算定を減額修正する要素

標準算定方式は、あくまでもなるべく多くのケースに当てはめられるよう、個別の父母の状況・子の状況などは考慮していない基準になります。
したがって、実際の事案において、それを修正すべき要素があれば、その要素によって、養育費を標準算定方式により計算できる養育費よりも増加させたり、減額したりすべき、ということもあります、
今回は、標準算定方式により計算できる養育費を減免すべきケースについて、典型的なものを触れていきます。
子がアルバイトをしている場合

仮に子がアルバイトなどにより収入を得ている場合、一般的にはその額は多額でないことが多く、小遣い程度に過ぎないものは養育費の算定に影響はないと考えられます。
これに対し、小遣いとはいえないような、多額の収入を子が得ており、子が自らの稼働能力によって収入が生じているという場合は、場合によっては子がもはや「未成熟子」とはいえず、養育費を支払う必要はない、というケースもあり得るところでしょう。
権利者の収入が義務者の収入を上回る場合
標準算定方式は、実はその前提として「子が収入の高い方の親と同居している」と仮定している計算になっています。したがって、子が父母のうち収入が高い方に監護養育されることとなった場合、そのより高収入の権利者が義務者に対して養育費を請求するという場合、義務者の養育費分担の額はより高くなってしまい、不公平な結果になってしまうのです。
そこで、権利者の方が義務者よりも高収入であるという場合は、権利者と義務者の収入が同一であると仮定して計算される費用を限度とすべき、という考え方があります。
このような考えに立つと、算定表で導かれる額を減額修正する要素として、権利者の高収入を考慮することになります。
義務者が既に子のライフライン・教育費を負担している場合

養育費とは、子の監護に要する費用の分担義務ですから、子のためにかかるライフラインの費用や教育費を、義務者の口座から引き落としているなど、養育費とは別途支払っているという場合は、当然毎月支払うべき養育費の額に対し、その分減額して考慮すべき、ということになります。
義務者も子を養育している場合
権利者のみならず、義務者も子を養育しているという場合、たとえば、権利者と義務者の間に3人子がいるが、長子と第二子は権利者、末子は義務者がそれぞれ親権を分けて帰属させた、というケースがあり得ます。
その場合、義務者自身も自身が養育する子の生活費指数を考慮する必要があるため、算定表通りの計算とはなりません。
当然、義務者自身が親権者として養育する子の生活指数を考慮し、養育費を減額して権利者に払うことが考えられます。
義務者が権利者との間の子以外に、扶養義務を負うべき者がいる場合

たとえば義務者に権利者以外の間に子がおり、その子を認知していた場合、義務者はその子に対しても扶養義務を有しています。
権利者との間に子がいるとしても、その認知した子の扶養義務を無視することはできないため、この認知した子の生活費を考慮する、すなわち権利者の側の子のために支払うべき養育費を減額すべきことになります。
同様に、義務者が再婚しており、新たな配偶者を得ていて、その配偶者を扶養しなければならない場合は、やはりその新たな配偶者に対する扶養義務を無視することはできないため、権利者に支払うべき養育費の額は減じる、ということになります。
権利者が再婚し、再婚相手が子を養子縁組した場合
この場合、養子制度の目的や、養父・養母(養親)が子の養育を全面的に引き受けたという暗黙の合意をした上で養子縁組しているものと考えられており、通常は実親である義務者の扶養義務は養親が一次的な義務を引き継ぐとされています。
ただし、養親が無資力である場合など、子に対し十分な扶養義務が果たせない場合には、実親である義務者がなお養育費の支払義務を負うと考えられています。
したがって、基本的には養親がいる場合には義務者の養育費は全額免れるものといえそうですが、養親の経済的状況によっては一部ないし全部の養育費をなお義務者が負う、すなわち減額の要素として働く可能性があります。
まとめ

今回は、給与所得者である配偶者の年収が900万円だった場合でも、算定表上の養育費から減額要素として働く事情について解説をしてきました。
実際の養育費算定に当たっては、様々な事情を考慮すべきということがあるので、算定表の数字は念頭に置きつつも、その修正要素がないかという点は、弁護士に相談するのも良いでしょう。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。