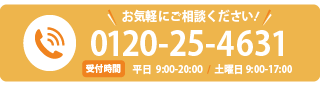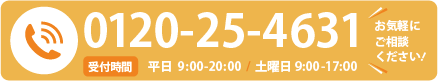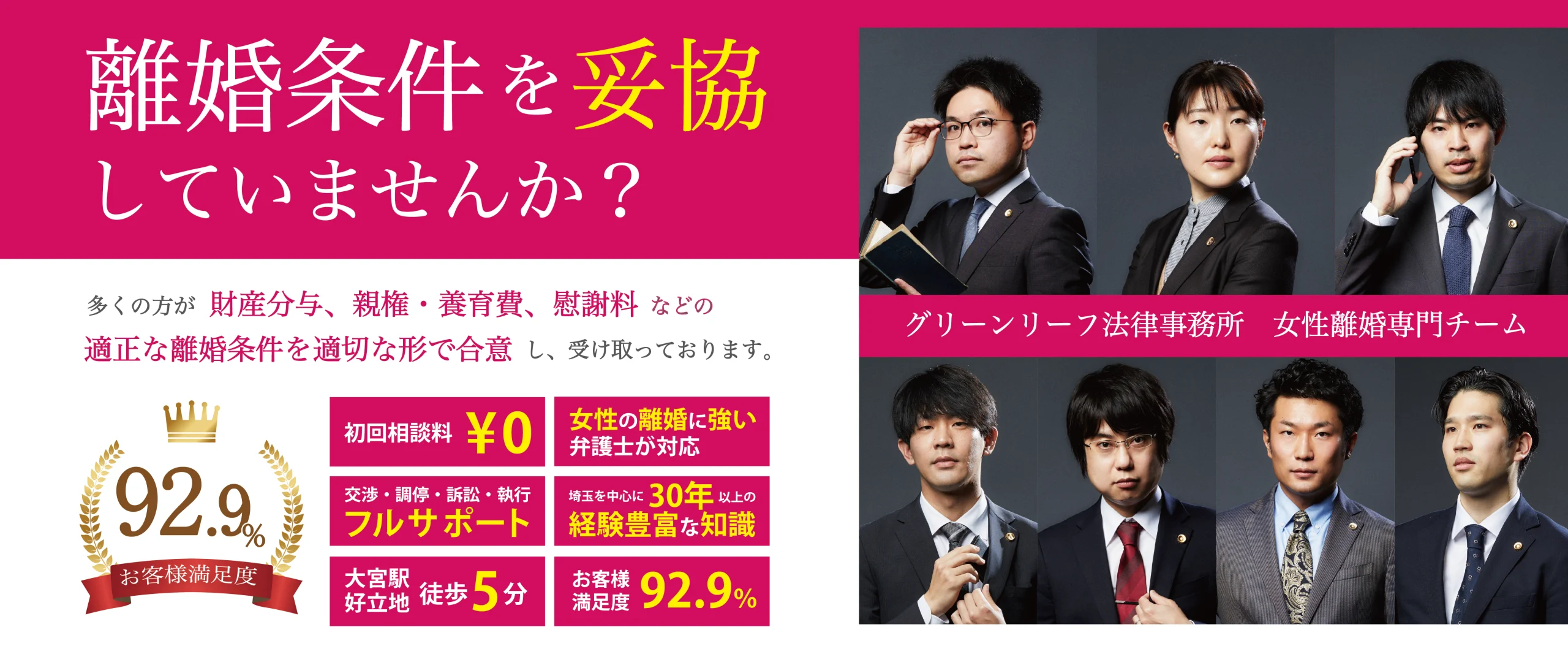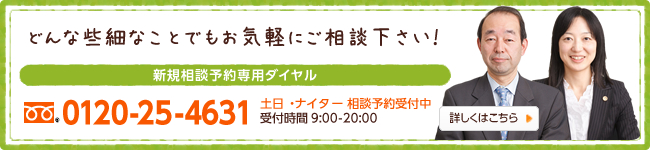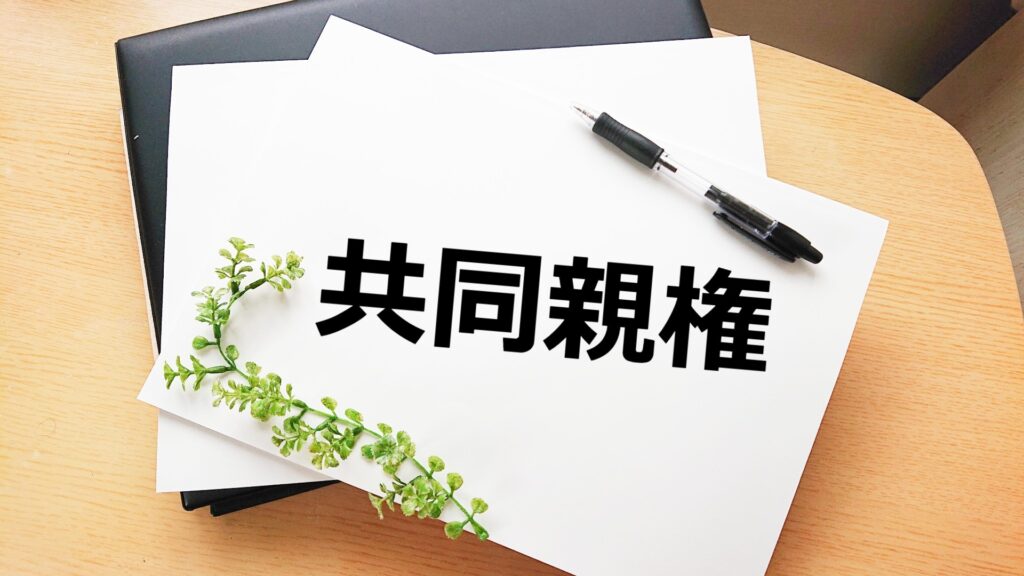
1.親権についてお悩みの方へ

「共同親権って、結局どうなるの?」
「離婚後の子育て、もっと大変になるんじゃ…」
「相手との関係が良くないのに、大丈夫?」
2024年5月、離婚後の「共同親権」を選択可能にする改正民法が成立しました。これは、日本の家族のあり方、そして離婚後の親子関係に大きな変化をもたらす可能性があります。
「子の利益」を最優先とするこの制度。
しかし、これまで単独親権が原則だった日本において、共同親権が導入されることに、期待とともに多くの疑問や不安の声が上がっているのも事実です。
特に、DV(ドメスティック・バイオレンス)や虐待の問題を抱えている方、相手方とのコミュニケーションに困難を感じている方にとっては、切実な問題でしょう。
このページでは、共同親権制度の導入によって具体的に何が変わるのか、どのような点に注意すべきなのか、そしてあなたとお子様の状況に合わせて、どのような備えができるのかを、離婚・親権問題に詳しい弁護士が分かりやすく解説します。
一人で悩まず、まずは正しい情報を知ることから始めましょう。
2.共同親権とは? 基本を理解する

これまで、日本では離婚後の親権は父母のどちらか一方のみが持つ「単独親権」が原則でした。
今回の法改正により、父母が協議して合意すれば「共同親権」を選択できるようになります。
協議が整わない場合や合意できない場合は、家庭裁判所が、個別の事情を考慮し「子の利益」の観点から、単独親権か共同親権かを判断します。
単独親権
従来どおり、父母の一方が親権者となり、子の監護・教育、財産管理などを行います。
共同親権
父母双方が親権者となり、協力して子の監護・教育、財産管理などを行います。
<留意点>
- 必ず共同親権になるわけではない
協議や裁判所の判断により、単独親権が維持されるケースもあり得ます。
具体的な裁判所の判断は、今後、事例の集積を待つ必要があります。
- 「子の利益」が最優先であること
どちらの親権形態が子の心身の健全な成長にとって最も望ましいかが、判断の最も重要な基準となります。
子の最善の利益について議論を深めていく必要があります。
- DV・虐待がある場合には単独親権となる可能性が高いこと
このような場合には、原則として単独親権と定めるとされています。
被害を受けている方は、適切な証拠をもって主張することが重要です。
3.共同親権導入で何が変わる?想定される変化と懸念点

共同親権の導入は、離婚後の親子関係に様々な影響を与える可能性があります。
(1)意思決定のあり方への影響
- 共同決定が原則となります。
進学、治療、引っ越しなど、子の重要な事項については、原則として父母双方の同意が必要となる可能性があります。
※日常的な行為や、急迫の事情がある場合は単独で決定可能とされています。
- 父母間の意見が対立した場合、意思決定が滞り、子の利益が損なわれる可能性があります。特に、関係性が良くない父母間では、些細なことでも対立が生じやすくなるかもしれません。
(2)養育費・面会交流への影響
- 共同で子育てに関わる意識が高まり、養育費の支払いや面会交流が円滑に行われるようになることが期待されます。
- 面会交流の実施を巡るトラブルが増加する可能性や、共同親権を盾に養育費の支払いを渋るケースも考えられ、共同親権のあり方についてはご家族に応じて将来のことを想定しておく必要があります。
(3)DV・虐待があるケースについて
- このような場合、原則として単独親権とされます。
つまり、法改正では、DV・虐待がある場合には裁判所が単独親権と定めるとされています。 - しかし、DV・虐待の事実については争いがあることもあります。
そのため、自身の主張が認めら、裁判所に適切に認定してもらうための立証活動が重要になります。 - 「共同親権」の名のもとに、加害者側が被害者や子に不当に関与し続けようとするリスクも指摘されています。
子どもの安全確保が最優先課題です。
(4)その他
連絡調整の負担増、再婚への影響、手続きの複雑化なども考えられます。
法律は成立しましたが、施行は公布から2年以内(2026年5月24日まで)とされており、具体的な運用ルール(ガイドライン等)はこれから詳細が定められていきます。
常に最新の情報を把握し、個別の状況に応じた対応を考える必要があります。
4.「子の利益」のために、弁護士ができること

共同親権制度の導入は、大きな変化です。
それゆえに、専門家である弁護士にご相談いただくメリットがあります。
(1)あなたの状況に合わせた最適な親権形態の検討
共同親権、単独親権、それぞれのメリット・デメリットを踏まえ、お子様とあなたの状況にとって何が「子の利益」に最も適うのか、法的な観点からアドバイスします。
DV・虐待の有無、お子様の年齢や意思、これまでの養育状況などを丁寧に伺い、証拠収集について、様々な角度からアドバイスを行います。
(2)離婚協議・調停・審判での的確な主張・立証
相手方との交渉や、家庭裁判所の手続きにおいて、あなたの代理人として、希望する親権形態(特に単独親権を希望する場合や、DV・虐待を理由とする場合)や、養育費、面会交流の適切な条件を獲得できるよう、法的主張と証拠に基づきサポートします。
(3)DV・虐待事案における安全確保と権利擁護
DV・虐待の事実を裁判所に理解してもらうための証拠収集のアドバイス、必要性が高い場合には保護命令の申立て、相手方との直接接触の回避など、あなたとお子様の安全を最優先に考えた対応を検討いたします。
共同親権が不適切であることの主張を行って参ります。
(4)共同親権を選択する場合の具体的な取り決めサポート
もし共同親権を選択する場合でも、将来のトラブルを防ぐために、意思決定のルール、連絡方法、緊急時の対応などを具体的に定めた合意書(離婚協議書、調停調書など)を作成することが極めて重要です。その作成をサポートします。
(5)最新の法改正・運用情報の提供と継続的なサポート
施行に向けた今後の動きや、実際の運用状況を踏まえ、常に最新かつ的確な情報を提供し、継続的にサポートします。
制度が変わっても、変わらないのは「お子様の幸せを願う気持ち」です。その気持ちを法的な力で支えるのが、私たちの役目です。
5.グリーンリーフ法律事務所が選ばれる理由
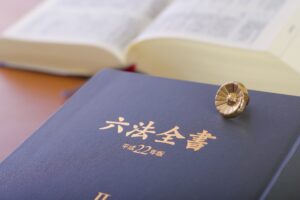
・初回相談60分無料
まずは気軽にご相談いただける体制を整えています。
・離婚・親権問題の豊富な解決実績
これまで多くの離婚、親権、面会交流、養育費の問題に取り組んでまいりました。複雑な事案にも対応可能です。
・共同親権制度への意気込み
最新の法改正の内容、議論の経緯、想定される運用について深く理解し、的確なアドバイスを提供します。グリーンリーフ法律事務所の弁護士は、家事調停委員との日頃の繋がりや家庭裁判所との協議会に参加するなどし、最新の情報収集に取り組んでおります。
・依頼者一人ひとりに寄り添う丁寧な対応
あなたのお話をじっくり伺い、不安や疑問に丁寧にお答えします。状況に合わせたオーダーメイドの解決策をご提案します。
・明確な弁護士費用
ご依頼いただく前に、費用について分かりやすくご説明します。お気軽にお尋ねください。
6.ご相談の流れ

①お問い合わせ
まずはお電話または専用フォームからお気軽にご連絡ください。(秘密厳守)
↓
②初回法律相談(無料)
弁護士が直接お話を伺い、共同親権制度の概要、あなたの状況における見通し、弁護士ができること、費用についてご説明します。
↓
③方針の決定・ご依頼
ご納得いただけましたら、委任契約を締結します。委任契約の締結時には詳しい内容をすべてお話しし、ご納得のうえでご契約に至ります。
↓
④サポート開始
相手方との交渉、調停・審判の申立て、証拠収集、書面作成など、方針に基づき具体的な手続きを進めます。解決に向けて丁寧に対応し、尽力いたします。
↓
⑤解決・アフターフォロー
解決時に、その後の紛争にならないよう条件を整えます。
解決後も必要に応じてアフターフォローをお伺いいたします。
7.弁護士からのメッセージ

はじめまして。弁護士の時田です。
「共同親権」という言葉に、大きな不安を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。法制度が変わる時、先行きが見えないことへの不安は当然のことです。
しかし、最も大切なのは、制度が変わっても、お子様の最善の利益を考え、お子様が安心して健やかに成長できる環境を守ることです。
私たちは、そのために法的な知識と経験を最大限に活かし、あなたとお子様にとって最善の道筋を見つけるお手伝いをしたいと考えています。
特に、DVや虐待の問題を抱え、「共同親権になったら、相手から逃れられないのではないか」と恐怖を感じている方もいらっしゃるかもしれません。
今回の法改正では、そのような場合に単独親権とする規定が設けられています。
諦めずに、ご自身の安全とお子様の未来を守るために、ぜひ一度ご相談ください。
8.よくあるご質問(FAQ)

-
共同親権になったら、どんなことでも相手の同意が必要になりますか?
-
日常的な行為(食事、日用品の購入など)や、子の急迫の事情(急な病気や怪我の手当てなど)については、単独で決定できるとされています。重要な事項(進学、医療、転居など)について、どこまで共同での決定が必要になるかは、今後の運用や個別の取り決めによります。
-
相手からDVを受けていました。共同親権になってしまうのでしょうか?
-
改正法では、父母の一方が他方からDVを受けるおそれ、子に虐待を受けるおそれがあると認められる場合には、裁判所は単独親権と定めなければならない、とされています。DVの事実を客観的な証拠(診断書、写真、録音、相談記録など)とともに適切に主張することが重要です。弁護士にご相談ください。
-
共同親権と養育費の関係はどうなりますか?
-
親権のあり方と養育費の支払い義務は、法的には別の問題です。共同親権になったからといって、養育費の支払い義務がなくなるわけではありません。むしろ、共同で養育に関わる責任から、支払いが促進される側面も期待されていますが、取り決めは明確にしておく必要があります。
-
共同親権になった場合、相手と直接連絡を取りたくありません。
-
父母間の連絡調整は共同親権における課題の一つです。弁護士を代理人として立てる、連絡調整支援機関を利用するなど、直接の連絡を避ける方法はあります。離婚時の取り決めでルール化しておくことが望ましいです。
-
いつから共同親権が選べるようになりますか?
-
改正法の施行は、公布日(2024年5月24日)から2年以内と定められています。具体的な施行日は政令で定められますが、遅くとも2026年5月までには施行される見込みです。
9.未来への備え、まずは弁護士にご相談ください

初回相談無料(ご来所 初回60分までご相談料は無料です。2回目以降のご相談料は、30分まで5000円(税込5500円)、以後30分まで5000円(税込5500円)です。)
秘密厳守・土日祝/夜間相談対応可能
共同親権制度についてのご不安、離婚や親権に関するお悩み、どんなことでも構いません。
専門家である弁護士が、あなたに最適な解決策を一緒に考えます。
[電話番号:048-649-4631 / 0120-25-4631 ]
(受付時間:平日 9:00~20:00 / 土曜 9:00~17:00)
[無料相談(または相談)予約フォーム]
(24時間受付)
お子様とあなたの明るい未来のために、今すぐ行動を起こしましょう。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
事務所概要
| 事務所名 | 弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 |
|---|---|
| 住所 | 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階(※ JR大宮駅西口から徒歩5分) |
| 電話番号 | 048-649-4631 |
| FAX | 048-649-4632 |
| 代表弁護士 | 弁護士 森田 茂夫(もりた しげお) |
| 登録番号 | 18964 |
| 所属弁護士会 | 埼玉弁護士会 |